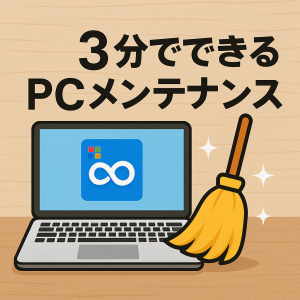近年、サイバー攻撃の手口はますます巧妙化しており、個人・企業を問わず、パソコンのウイルス感染リスクは高まっています。 「自分は大丈夫」と思っていても、ちょっとした油断が大きな被害につながることも。 この記事では、情報システム部門の視点から、日常業務の中で実践できるウイルス感染予防のポイントをわかりやすく解説します。
なぜ今、ウイルス対策が重要なのか
テレワークの普及やクラウドサービスの活用により、私たちの業務環境はかつてないほど柔軟で便利になりました。 しかしその一方で、セキュリティの境界線が曖昧になり、攻撃者にとっては“狙いやすい隙”が増えたとも言えます。 特に「ランサムウェア」や「情報窃取型マルウェア」は、個人の端末を足がかりにして企業全体へ侵入するケースもあり、被害は金銭的損失だけでなく、信頼や業務継続性にも深刻な影響を及ぼします。
さらに、攻撃者は「人の心理」を巧みに突いてきます。 「急いで対応しなければ」「上司からの指示かもしれない」といった焦りや思い込みが、感染のきっかけになることも。 だからこそ、今こそ“個人レベルの対策”が求められているのです。 セキュリティは専門部署だけの責任ではなく、全社員が“最前線”に立っているという意識が重要です。
ウイルス感染の主な経路
1.不審なメールの添付ファイルやリンク
業務メールに紛れて届く不審な添付ファイルやリンクは、見慣れた形式で送られてくるため、つい開いてしまいがちです。 特に「請求書」「至急対応」などの件名は注意が必要です。
2.偽のソフトウェアやアップデートファイル
公式サイトに似せたデザインで信頼を装い、インストールを促してくるケースがあります。 セキュリティソフトやブラウザの更新通知に見せかけた偽メッセージも増えています。
3.USBメモリなどの外部デバイス
社外で使用されたUSBメモリには、マルウェアが潜んでいる可能性があります。 社内ネットワークに接続することで、感染が広がる危険性があります。
4.セキュリティが不十分なWi-Fi接続OSやソフトウェアの脆弱性を突いた攻撃
公共のWi-Fiは暗号化が不十分な場合が多く、通信内容が盗み見られるリスクがあります。 VPNの利用や、業務用端末での接続制限が求められます。また、古いバージョンのソフトウェアには、既知の脆弱性が残っていることがあります。 攻撃者はそれを狙って、自動的に侵入を試みることがあります。

今すぐできるウイルス感染予防の6つの基本
ウイルス対策は、特別な知識がなくても始められます。以下の6つは、すぐに実践できる基本です
・社内ルールに沿ったセキュリティ設定を守る
パスワードポリシーやアクセス制限など、社内のセキュリティルールを遵守することが、組織全体の防御力を高めます。
・ウイルス対策ソフトを常に最新に保つ
定期的なスキャンだけでなく、リアルタイム保護機能を有効にすることで、未知の脅威にも対応できます。
・OS・アプリのアップデートを怠らない
自動更新を有効にし、定期的にアップデート状況を確認しましょう。 特にブラウザやPDFリーダーなど、日常的に使用するアプリは要注意です。
・不審なメールは開かず、添付ファイルもクリックしない
差出人が知っている名前でも、なりすましの可能性があります。 件名や文面に違和感がある場合は、開封前に確認を。
・信頼できないサイトからのダウンロードを避ける
フリーソフトや拡張機能のインストールは、公式サイト以外から行わないようにしましょう。
・USBメモリはスキャンしてから使用する
使用前には必ずウイルススキャンを行い、社内で許可されたデバイスのみを使用しましょう。

メール・添付ファイルの取り扱い注意点
メールは日々の業務で最も多く使われるツールですが、それだけに攻撃の温床にもなりやすいです。 「請求書」「至急対応」などの件名で送られてくるメールは、心理的な焦りを誘い、開封を促します。差出人が知っている名前でも、なりすましの可能性があるため、メールアドレスや文面の違和感に注意を払いましょう。
特に、本文中のリンクには注意が必要です。短縮URLや、正規のドメインに似せた偽URL(例:micr0soft.comなど)は、見た目では判断が難しいこともあります。リンクをクリックする前に、マウスオーバーでURLを確認する習慣をつけましょう。 また、添付ファイルは開く前に必ずウイルススキャンを行い、業務上必要な場合でも、少しでも不審に感じたら情報システム部門に相談することが大切です。

USBメモリ・外部デバイス利用時の注意
外部から持ち込まれたUSBメモリには、マルウェアが仕込まれている可能性があります。特に展示会やセミナーなどで配布されるノベルティ型USBは、見た目に安心してしまいがちですが、内部に不正なプログラムが含まれているケースも報告されています。
使用前には必ずウイルススキャンを行い、社内で許可されたデバイスのみを使用しましょう。業務用PCと私物デバイスの接続は原則禁止です。 また、外部デバイスの使用履歴を記録することで、万が一感染が発生した場合の追跡が容易になります。情報システム部門と連携し、使用ルールを明確にしておくことが、組織全体の安全につながります。
ソフトウェアとOSのアップデート管理
古いバージョンのソフトウェアには、既知の脆弱性が残っていることがあります。攻撃者はそれらの情報をもとに、特定のバージョンを狙って攻撃を仕掛けてきます。 そのため、自動更新を有効にし、定期的にアップデート状況を確認することが重要です。
特にブラウザやPDFリーダー、メールクライアントなど、日常的に使用するアプリは要注意です。更新通知を見逃さず、社内で使用するソフトウェアの一覧を定期的に棚卸しすることで、不要なアプリの削除や更新漏れの防止につながります。 また、アップデート後の動作確認も忘れずに行いましょう。更新によって設定が初期化される場合もあるため、セキュリティ設定が維持されているか確認することが大切です。

パスワード管理と多要素認証の活用
「123456」や「password」などの単純なパスワードは危険です。攻撃者はこうした“よくあるパスワード”をリスト化し、自動的にログインを試みる「ブルートフォース攻撃」を行います。 パスワードは定期的に変更し、使い回しを避けましょう。異なるサービスには異なるパスワードを設定することが基本です。
さらに、可能な限り多要素認証(MFA)を導入することで、セキュリティを強化できます。MFAとは、パスワードに加えて、スマートフォンの認証コードや生体認証など、複数の要素で本人確認を行う仕組みです。 これにより、万が一パスワードが漏洩しても、第三者による不正アクセスを防ぐことができます。社内システムへのログインやクラウドサービスの利用時には、MFAの導入を積極的に検討しましょう。
社内ネットワークを守るために
社内ネットワークに接続するすべての端末が、セキュリティリスクになり得ます。特に、私物端末や外部委託先の機器が接続される場合は、事前のセキュリティチェックが不可欠です。 VPNの利用やアクセス制限、ログ監視など、組織全体での対策が重要です。
また、ネットワークの構成を定期的に見直し、不要な接続や開放ポートを閉じることで、攻撃の足がかりを減らすことができます。 情報システム部門だけでなく、現場の担当者が「どの端末がどこに接続されているか」を把握することも、セキュリティ強化につながります。 個人の意識と組織の仕組みが連携することで、強固な防御が実現します。
感染が疑われたときの初動対応
万が一、ウイルス感染が疑われた場合は、迅速かつ冷静な対応が求められます。以下の初動対応を徹底しましょう
ネットワークから切り離す
LANケーブルを抜く、Wi-Fiを切るなどして、感染拡大を防ぎます。
すぐに情報システム部門に連絡する
自分で対処しようとせず、専門部署の指示を仰ぎましょう。
他の端末との接続を避ける
USBメモリや共有フォルダなどを使って、他の端末に感染が広がるのを防ぎます。
自分で駆除しようとせず、専門対応を待つ
市販の駆除ツールを使うことで、かえって状況が悪化することもあります。 正しい手順での対応が、被害を最小限に抑える鍵です。

安心・安全なPC利用のために
ウイルス感染は、ほんの一瞬の油断から始まります。 「自分は大丈夫」「うちの会社は狙われない」と思っていても、攻撃者はそうした隙を狙ってきます。 だからこそ、日々の業務の中で“当たり前”にセキュリティ対策を意識することが、最も効果的な予防策です。
この記事で紹介した対策は、どれも特別な知識や技術を必要とするものではありません。 メールを開く前に一呼吸置く。USBメモリを使う前にスキャンする。パスワードを見直す。 そんな小さな行動の積み重ねが、組織全体の安全を守る大きな力になります。
また、万が一感染が疑われた場合も、慌てず冷静に初動対応を取ることが重要です。 「報告しづらい」「自分のせいかも」と感じる必要はありません。 セキュリティは“個人の責任”ではなく、“チームで守るもの”です。
私たち一人ひとりが、セキュリティの「最前線」に立っているという意識を持ち、 安心して働ける環境づくりに貢献していきましょう。 この冬、節電と同じように、PCの安全対策も“無理なく、賢く”取り入れてみてください。
終わりに
アイング株式会社では、日々の業務を支えるすべてのスタッフが、安心して働ける環境づくりを何よりも大切にしています。 セキュリティ対策は、専門部署だけが担うものではなく、現場で働く一人ひとりの意識と行動が鍵となります。だからこそ私たちは、情報システム部門と現場が連携し、誰もが“無理なく、自然に”取り組める予防策の浸透を目指しています。
ウイルス感染のリスクは、目に見えないからこそ軽視されがちです。ですが、実際の被害は業務の停滞や顧客との信頼関係の揺らぎなど、目に見える形で現れます。そうした事態を未然に防ぐためにも、「ちょっとした注意」「一呼吸置く習慣」「報告しやすい空気づくり」が、何よりも重要です。
アイング株式会社では、セキュリティを“守るもの”ではなく、“育てるもの”と捉えています。 それは、ルールや仕組みだけでなく、働く人の気持ちや行動が積み重なってこそ、真に強固な防御が生まれるという考え方です。 たとえば、USBメモリを使う前にスキャンする、メールのリンクをクリックする前にURLを確認する、パスワードを見直す──こうした小さな行動が、組織全体の安全を支える大きな力になります。
また、万が一感染が疑われた場合も、誰かを責めるのではなく、冷静に対応し、チームで乗り越える姿勢を大切にしています。 「報告しづらい」「自分のせいかも」と感じる必要はありません。 セキュリティは“個人の責任”ではなく、“チームで守るもの”です。 そのために、私たちは「相談しやすさ」「対応の速さ」「安心して報告できる文化づくり」に力を入れています。
この冬、節電と同じように、PCの安全対策も“無理なく、賢く”取り入れてみませんか。 アイング株式会社は、すべてのスタッフが安心して働ける環境を守るために、これからも現場に寄り添ったセキュリティ支援を続けてまいります。 この記事を読んだあなたの“ちょっとした気づき”が、組織全体の安全を支える第一歩です。